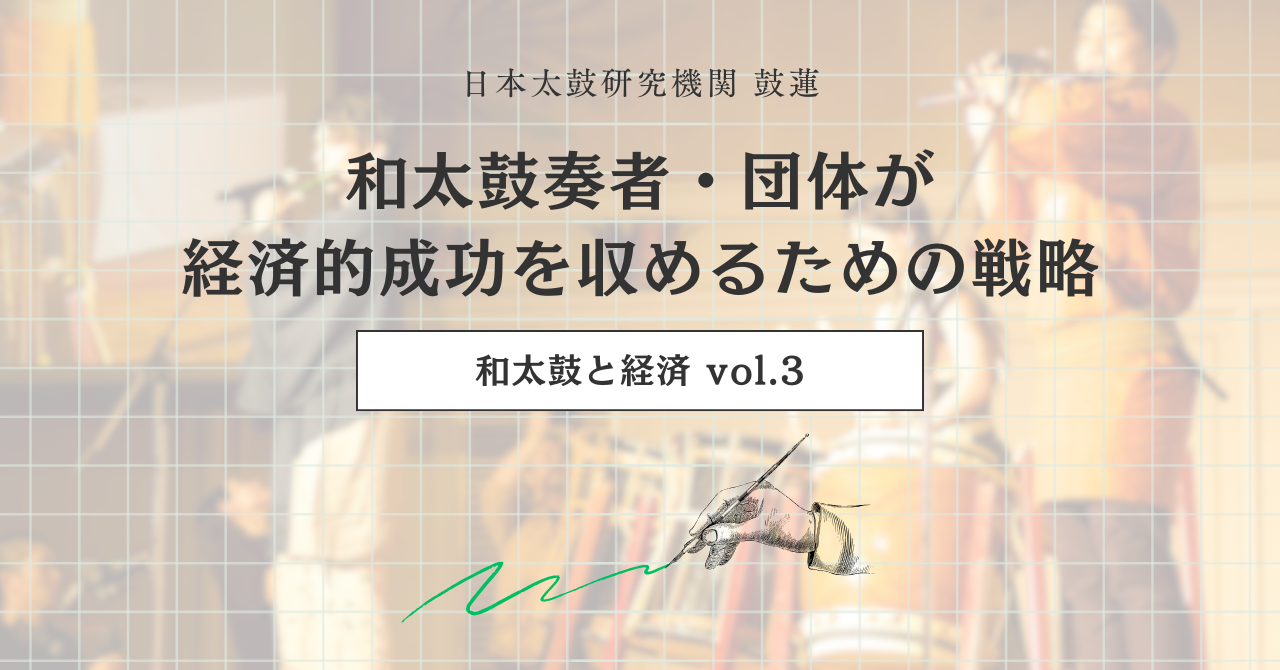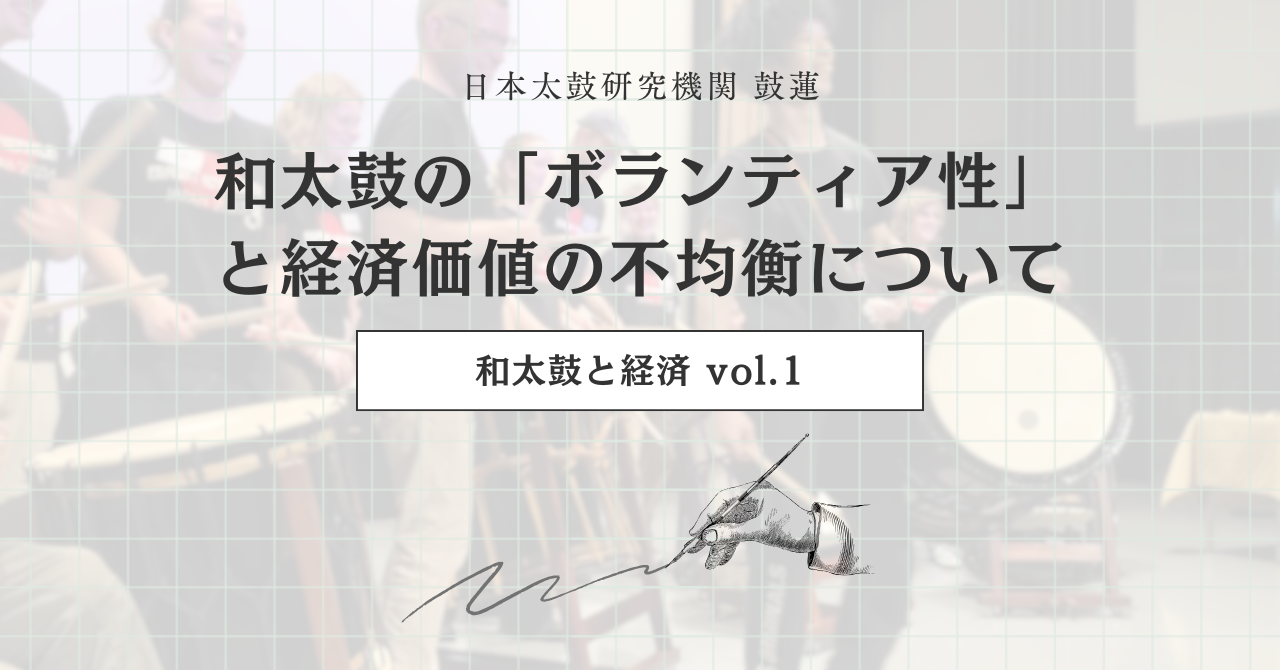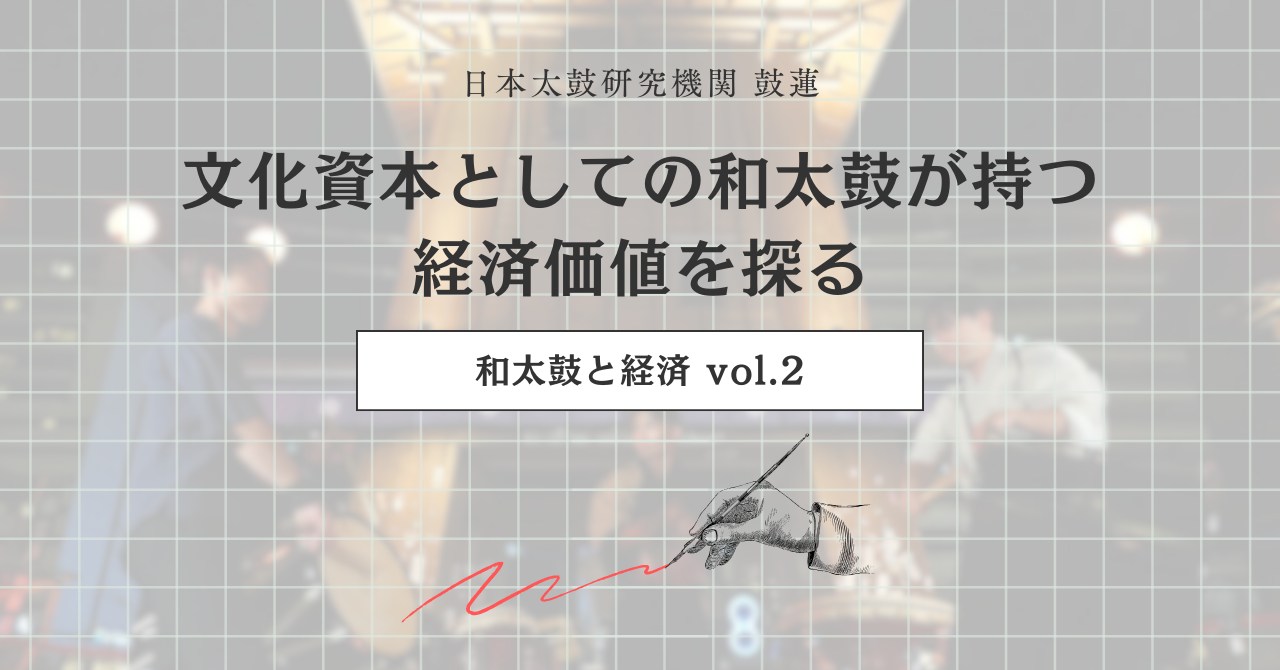はじめに:和太鼓奏者における課題としての『経済的報酬』
和太鼓奏者・団体が直面する問題の一つである「ボランティア性の高さと低報酬での演奏」について『和太鼓の「ボランティア性」と経済価値の不均衡について』にて具体的に問題定義をし、その課題を解決するために『文化資本としての和太鼓が持つ経済価値を探る』で和太鼓の持つ文化資本と経済価値について述べた。
2つの記事を通して論じてきた「ボラティア性」という課題は『和太鼓における商業的活動』においての課題であり、実のところ『ボランティア・低報酬』を課題だと感じていない和太鼓奏者も多い。筆者もまた、商業領域における課題としては問題視しているが、文化的・社会的側面においてはむしろ最も重要で、他の楽器において類を見ないほど唯一無二な価値だと思っている。
複数の太鼓を並べて集団で演奏する「和太鼓演奏=組太鼓」そのものは「戦後生まれた創作芸能及び芸術表現活動」であり、『和太鼓』とは創作太鼓芸という比較的新しい音楽である。古来より継承されてきた芸能の中で行われる太鼓演奏は素朴で即興性の高いものであった。
しかし、和太鼓という楽器そのものが内包する歴史的かつ文化的なコンテクスト(文脈)が「和太鼓演奏=伝統的な芸能」という認識を生み、祭事などで見られるお囃子の公共的な性質も相まってその認識を強めていった。そしてその認識が和太鼓を演奏して表現活動を行う和太鼓奏者の経済活動に支障をきたすようになってしまっている。
強烈な文化的側面が内包するからこそ、一つの楽器の中でそれぞれの立場で対立が起こり、結果として和太鼓演奏に適切な価格を付けにくい現状を生み出してしまった。そして和太鼓及び和太鼓奏者は芸術と商業の狭間で身動きが取れなくなっているのが現状である。
筆者及び弊団体は『文化資本としての和太鼓が持つ経済価値を探る』の中で「和太鼓の文化的・社会的な価値の純粋性」を維持しながら、経済活動と結びつける方法として「和太鼓を地域産業と結びつけ、人を動かすための風として和太鼓を活用する」モデルを提示した。
そして、情報の消費によって機能する現代の経済モデル「生成型経験経済」に適応させることで和太鼓奏者は自身の演奏によって引き起こせる経済波及効果を理解し、それを武器に適正価格で評価を受けることができるようになる。
本稿は「文化と経済・芸術と商業で揺れる和太鼓奏者が資本主義に適応する方法」として和太鼓奏者が『文化的活動』と『経済的活動』をどのように区別・管理し、芸術としての純粋性を保ちながら、経済的報酬を受け取るための商業性をしっかりとサービス化し、和太鼓奏者として生きていける案を提示する。
和太鼓奏者が提供できる『価値』とは何か?
「和太鼓奏者が提供できる価値とは何か?」という質問に対して、明確な価値を定義して回答することができるだろうか?また、その価値がクライアント(演奏依頼主)に対して『報酬を支払うに値する対価』として納得できる内容のものだろうか?
これは和太鼓奏者のみならず、あらゆる表現活動をしているアーティスト全般に言えることだが、多くの場合 『自身の技術』を価値として差し出し 、 依頼主の期待する結果に伴わなかったとしても 「報酬はもらえるもの」だと認識している。
もちろん、クライアントが『演奏技術』に対して価値を見出し、それを披露してほしいというのが目的であれば、報酬を得られるのは当然の結果であり、そこに対して何も問題はない。
しかし、そういったケースは非常に稀であるという点は理解しておかねばならない。なぜなら、クライアントにはクライアントの 「依頼をする目的」 、 があり 「達成したい目標」 があるからだ。
筆者はこれまで和太鼓奏者におけるボランティア性・低報酬が際立つ要因として、和太鼓が形成する文化の中に内包される公共財としての側面や、演奏技術の差異が分かりにくい点などから生じる経済価値を定める尺度の不在を提示してきたが、それだけがこの問題を引き起こしているわけではない。
和太鼓奏者が「自身の提供できる価値」について公共的なイメージのあるお囃子や呼び込みで使用されるような単調な音(これもまた深い歴史と価値のある側面ではあるが)とどう異なるのか。
ここをしっかりと言語化し、その価値を提示できていないからこそ、価格が不透明な状態となってしまい、結果としてクライアント側が認識するイメージが価格に反映されてしまうのである。
では具体的にどのような戦略を経てれば「適正価格で依頼を受けられるようになるのか?」を考察していく。
1. 資本主義経済の構造を理解し、適応する
ビジネスにおいて 「売る相手がたくさんいる市場に参入すること」 、 それは和太鼓奏者・団体にも言えることである。独自性のある強みを持ち、対価を得るに値する価値を保有していたとしても、その価値を求める相手がいなければ何もできない。
そして自身の価値を売り出す前に押さえておきたいのが『経済活動のルールに則る』というビジネスの原則である。経済とは『価値と価値の交換』という取引が無数に連なり連鎖する場であり、和太鼓奏者もまた『価値と価値の交換』という原理原則に適応しなければならない。資本主義に適応することは経済的成功を得るために避けては通れない重要な要素だ。
ここで資本主義経済の特徴について簡単に整理しておこう。
資本主義(Capitalism)は、私有財産制、市場経済、競争原理、利潤追求の原則を基盤とした経済体系である。市場は固定的ではなく、イノベーションと成長によって変化し続け、流動的な特性がある。これは和太鼓奏者が属する市場においても当てはまり、市場の中で経済報酬を受け取るのであれば、資本主義経済に適応する必要がある。
また、経済活動を引き起こすために必要な「価値」は『需要のある価値』でなければならない。どれだけ超絶技巧な演奏ができても、需要がなければ埋もれてしまう。
『お金を払いたい顧客がどれだけいるか』『競争相手(他の演奏者、他のエンタメコンテンツ)との価格競争に耐えうるか』『価値を伝える方法があるか』を客観的に分析し、自身の価値を適切に届け、選ばれるための仕組みを作ることが和太鼓奏者・団体が社会的及び経済的な成功を得るために必要となる。
| 資本主義の特徴 | 和太鼓演奏ビジネスへの適用 | 具体的な例 |
|---|---|---|
| ① 私有財産制 | 和太鼓奏者や団体が楽器、スタジオ、ブランド、知的財産を私有し、利益を生む | ・自分の和太鼓を所有し、演奏活動をする ・スタジオを借りて教室を開く ・自作の楽曲や演奏動画の著作権を管理 |
| ② 市場経済 | 需要と供給によって演奏の価格やレッスン料金が変動 | ・人気奏者のライブチケットが高額でも売れる ・生徒が増えれば、レッスン料が高くなる |
| ③ 競争原理 | 他の和太鼓奏者やエンタメ業界と競争し、演奏技術や演出で差別化 | ・伝統的な和太鼓 vs モダンな和太鼓パフォーマンス ・SNSを活用して認知度を高める |
| ④ 利潤追求 | 演奏活動だけでなく、レッスンやコラボ商品などで収益を拡大 | ・公演チケット販売 + オンライン和太鼓教室 ・企業スポンサー契約 |
| ⑤ イノベーションと成長 | 新たな技術やビジネスモデルを導入し、持続的に発展 | ・YouTube・Spotifyで和太鼓の音楽配信 ・VR技術を活用した演奏体験 |
和太鼓奏者並びに和太鼓団体として活動し、経済的な成功をおさめたいと考えているのであれば『資本主義経済への適応』は避けて通れない。『需要のある価値』を生み出し、それを欲しいと思う顧客がいる市場に参入しなければビジネスとしての成功は得られないのである。
そのために、自身の価値を言語化した次に『自身の価値を欲しいと思う市場を見定め、そこに参入する』必要がある。
では、具体的にどのような市場に参入するべきなのだろうか?その答えを本記事で提示することはできない。なぜなら市場とは複雑であり、一見同じに見えても異なるコンテクストを持ち、異なるレイヤーにあるプレイヤーが絡み合い重なり合いながら形成されているからである。
結局のところ『資本主義の世界に参入する覚悟』をどれだけ持てるかどうか?が重要であり、適応するために自身のマインドをしっかりとコントロールすることが和太鼓奏者には求められる。
2. 自身が提供できる価値は何かを言語化する
和太鼓奏者のみならず、己の技術を価値としてクライアントに提供し、その対価として報酬をもらう経済活動を行うのであれば、その活動の規模が大きくとも小さくとも『自信が提供できる価値を明確に言語化し、どのようなメリットが得られるのか』を具体的に提示できる必要がある。
まず最初に「できること」と「できないこと」を分別する。この段階では抽象度は高くても良い。実際に何ができるのかを棚卸しよう。
さらにそこから「必ずできること」「条件がそろえばできること」で区別する。できないことも「(この先できるようになるために改善しているが)今、できないこと」「(できるようになる可能性はあるが)できないこと」「この先もできないこと」で分別する。
そしたら今度はそれを具体的なカテゴライズに当てはめて整理する。すると下記のような表のように「できること」が可視化できる。
| カテゴリー | 必ずできること | 条件がそろえばできること | この先できるようになること | できないこと |
|---|---|---|---|---|
| 技術価値 | ・〇〇流派の演奏 ・ソロ演奏 ・アンサンブル |
・即興演奏 ・特定の流派の奏法 ・他和楽器の演奏 |
・洋楽器とのコラボ ・他ジャンルとのコラボ |
・舞踊や唄を自身で演じながらの演奏 |
| 演出・表現価値 | ・作曲 ・舞台演出の基礎 MC |
・照明による演出 ・小道具による演出< |
・他ジャンルを組み合わせた演出 |
・衣装の制作 ・デザイン全般の演出 |
| 教育・指導価値 | ・初心者向けワークショップ | ・和太鼓教室の講師 ・学校での技術指導 |
・和太鼓教室のカリキュラム制作 ・企業研修向けプログラム |
・音楽理論の専門指導 ・他和楽器の指導 |
| 文化価値 | ・地域イベントでの演奏 ・伝統行事での演奏 |
・地域のお囃子への参加 ・地域芸能の補佐 |
・文化財認定の活動 ・文化政策への関与 |
・文化政策決定への関与 |
| 商業価値 | ・祝賀会等での演奏 ・イベントでの演奏 |
・企業案件での演奏及び対応 ・集客施策への参加 |
・集客のためのプロモーション ・楽曲提供 |
・企業案件における演出の総合プロデュース |
そして、そこから『できること』に注力して提供できる価値を具体的に振り分けていく。例えば「技術価値」をより具体的にするのであれば以下のような問いに答えられるようにしておくと良い。
- 演奏時間は最小何分〜最大何分まで対応できるのか?
- 最小何人で最大何人編成での演奏ができるのか?
- 他の和楽器(篠笛、三味線、箏、尺八、琵琶など)とのアンサンブルは可能なのか?
- 魅せる演奏(持久力を要する連打、速打ち、衣装替え、舞踊、唄など)の可否
- 演奏できる場所のレパートリー(劇場、野外、式場、小さなお店、スタジオなど)
- 保有する楽器(大太鼓、長胴太鼓、締太鼓、篠笛、鉦、チャッパなど)
この「具体性」が明確であればあるほど、『提供できる価値』を言語化しやすくなり、自身の価値を訴求するための戦略が立てやすくなる。
他にも「演出のディレクションも可能」「他の舞台芸術とのコラボが可能」「ワークショップや研修プログラムのカリキュラム作成が可能」「文化的背景を解説するセミナーを交えた演奏が可能」「企業イベントやPR案件への対応及び和太鼓領域のディレクションが可能」「イベントの集客企画が可能」など具体性を持たせた形で『できること』をリスト化することが大切である。
そして、それらの組み合わせこそが『他の奏者や団体とは異なる独自性』となる。
3. 自身の価値が生きる市場を選択し、参入する
自身の価値を商品化し、ブランドとして市場に参入するには、自身の価値が『どの市場に適しているのか?』を明確にする必要がある。そして、市場を細分化し、生きる場所を見つけることで和太鼓奏者としての活動を加速的に進めることができる。
ここでは、市場を選択し、参入するまでの一連の流れを解説する。
ステップ1:市場をセグメントする
まず最初に『自身の価値を提供する市場』の選択をする必要がある。自身の価値を闇雲に宣伝することは悪いことではない。しかし、自身の価値をターゲットに訴求するには多くのコストがかかる。
そこで、自身の価値を必要とする(ニーズがある)市場に狙いを定め、そこにコストを割いたほうが同じ時間を使いながら効率よく営業活動が行えるようになる。
消費者全体を共通のニーズ、属性、価値観などに基づいて分類し、特定のグループに分ける作業のことを『市場のセグメンテーション』と呼ぶ。
例えば和太鼓を含む音楽市場は単に「音楽ファン」だけで構成されているわけではない。以下のような軸でセグメント化が可能である。
- ニーズ軸:伝統文化への関心、エンタメ消費、身体性を重視する層など
- 行動軸:フェスティバル参加者、ライブハウス来場者、教育プログラムの参加者
- 地理軸:国内(都市部/地方)、国外(特に欧米・アジア市場)
- 心理軸:「和」の世界観に魅力を感じる層、スピリチュアル・トランス体験を求める層…など
自身の提供できる価値を棚卸しし、整理整頓・言語化したら、その価値が『誰に刺さるのか』を明確にし、そのターゲットが『どの市場に属するのか』を仮説立てしていく。
先にお伝えしておくと、この『セグメント』に関する作業は一気に作り込む必要はない。というのも、最初から市場が明確であれば狙いを定めやすいので絞り込めるが、多くの場合、誰に対してニーズがあるのかは不明確なものだ。筆者もセグメンテーションを行う際は『大まかな市場(業種や業界など)で一回区切り、そこから『自身の提供する価値を求める想定される人のリスト化』を大まかに行う。
市場をセグメントすると、自身の価値に対して必要だと思ってくれる人たちの『ニーズが属性ごとに異なる』ということが浮き彫りになり、攻め方(営業アプローチの仕方)がぼんやりと浮かんできやすくなる。そうなればこのフェーズは完了だ。
重要なのは 『大きな市場を共通項でグループ分けし、それぞれのニーズの違いと訴求方法の違いがわかるようになること』 である。
また、最後に和太鼓奏者並びに和楽器奏者が自身の価値を提供する市場をセグメンテーションするにあたって最も重要な視点を記して次の項目へ向かいたいと思う。
『和太鼓の「ボランティア性」と経済価値の不均衡について』でも述べた通り、(特に)和太鼓は公共性の高さから『無料で体験できるもの』というイメージが強い。また、舞台芸術としての市場もあることにはあるが、消費者のパイは多くない課題もある。そのため、セグメンテーションする際は『経済的報酬を受けるに値する価値を提供できる市場』を軸に整理することをオススメしたい。
自身の提供する価値が『具体的にどのような問題を解決』し『どのようなメリットをもたらす』のかを言語化できていれば、自ずと自身の提供する価値が最も求められる市場が(おぼろげながらも)見えてくるはずだ。
ステップ2:自分の価値が“刺さる市場”を選ぶ
市場を整理し、自身の価値が刺さりそうな市場を分別したら、「自分の価値が“刺さる市場”を選ぶ」フェーズに入る。セグメンテーションをしていると、その段階で『多分この市場が刺さりそうだな』という仮説が生まれてくるため、ステップ1とステップ2は事実上同タイミングで行われる傾向にある。
そのため、必ずしも『セグメントしてから、刺さる市場を選んで…』といった手順を踏まなければいけないわけではない。
また、『刺さる市場=経済的報酬を得やすい市場』になっているかどうか吟味する必要がある。
和太鼓奏者・和楽器奏者のみならず、あらゆる表現を生業とするアーティスト及びクリエイターにありがちな思考として『自身の技術』に対し価値を置き、価格を設定してしまうケースがある。
技術は確かに重要だ。しかし、それは必ずしも経済的報酬と直結するわけではない。
大切なのは 『顧客が求めること(目的の達成・問題解決・経済的メリットの享受・社会的メリットの享受など)』 を 達成することであり、そのために技術が どのように活用されるのか、技術によってどのような影響を及ぼし、状況を変化させるエネルギーを起こすのかという問題解決に自身の技術が役立つかどうかであり、価格はここに宿る。
そして、その『変化』が顧客にとって『経済的報酬を支払うに値する価値』であることが重要である。
ここで改めて『自分の価値が刺さる市場』について考えてみよう。
『自分が提供できる価値=自身の技術で解決できる問題』として考えた時、自分の価値を必要とする顧客は【どこの市場にいるのだろうか?】という問いを繰り返し自問自答してみてほしい。
その結果導き出された市場があなたが参入するべき市場である。
ステップ3:見せ方(=価値の届け方)を言語化する
さて、参入する市場が定まったら次にやるべきことは『自身の価値を見込み客に向けてどうアピールするか』という届け方のフェーズだ。
先に伝えておくと、ステップ3とステップ4はほぼ同タイミングで行われる。が、どんな状態であっても『見せ方を言語化→見せ方を届ける方法』の順番は変わらない。そのため、既に自身の価値を見込み客にアピールする方法が脳裏に浮かんでいるのであれば、それを届ける手段(マーケティング)へと移行しても構わない。
自身の価値を整理整頓し、しっかりと言語化できているのであれば、ここのフェーズは最終確認のようなものだ。しかし、重要なのは『見込み客に伝わる伝え方』である。
「なぜその商品・サービスが顧客にとって唯一無二なのか」を明確に伝える価値の訴求方法が定まっていなければ、届ける手段を選ぶことはできない。
具体的に3つの段階を踏むと整理しやすく、自身の価値を具体的な商品へと落とし込みやすい。
- 【届ける価値=顧客が感じる意味・変化】 の定義を言語化する
- 【視覚・聴覚・身体感覚の設計=世界観を明確にする」
- 【世界観=ブランド】と【売れるパッケージ=商品】」の統合(ステップ4に行く前の最終準備)
① 【届ける価値=顧客が感じる意味・変化】 の定義を言語化する
ここで改めて「提供できる価値」について更に見つめ直し、自身が提供する価値によって『顧客が感じる意味・変化』について言語化をする。ここで重要なのは『必ずしも届けるものは音だけではない』という視点と、顧客=鑑賞者ではないということを意識して言語化することだ。
| 顧客が得る価値 | 意味の構造 |
|---|---|
| 感動 | 音・動作・表情の一体感が心を揺さぶる |
| 一体感 | 共同で演奏することで連帯感が生じ、場が繋がる |
| 自己解放 | 打ち鳴らすことで内側からエネルギーが湧く |
| 畏敬・神聖さ | 太古からの響きを身体で受け取る感覚 |
| 美 | 動作・衣装・所作・構成美 |
上図のように『顧客が得る価値』に対して、その価値に意味が生じる構造をまとめておくと、次のフェーズに進みやすくなる。また、ここで言語化がうまくできていると、単価を上げる際の説得力が増す。
また、上図ではかなり広い範囲(例えば「一体感」という価値は観客よりも演者側の方が抱きやすい)をカバーしている例のため、実際に顧客が得る価値の構造を言語化する際は『自身の商材をある程度イメージしておくこと』は欠かせない。
人前で演奏するのか?技術を教えるのか?
しっかりと吟味し、イメージを固めながら言語化を進めるのを推奨したい。
② 視覚・聴覚・身体感覚の設計=世界観を明確にする
さて、では次に自身のが提供できる価値を視覚的・聴覚的・身体感覚的に理解できるように世界観を明確にする設計を行う。この設計が『世界観=ブランド』の基盤となる。
【視覚:ビジュアル・世界観の統一】は衣装、所作、演出、ロゴ、フォントなど、視覚的に目につく領域を明確にし、ルールとして体系化する構造の設計である。一貫性があればあるほど世界観を理解してもらいやすくなる。また、ここが明確であれば組織の拡大や拡張を行なった際もスムーズに行動に移せるようになる。
【聴覚:音の“意味”と“空間性”を設計】は構成、音色、空間に対して『提供するサービスの特徴となる領域』を設計する。例えば『楽曲』や『舞台』などが当てはまる。聴覚的な領域は既に基盤ができているケーズも珍しくないだろうが、改めて世界観と一致しているか?という視点で見直してみよう。
【身体感覚:演者の“存在”を設計】は『存在自体から発せられる魅力』に対する構造上の設計である。筋肉・呼吸・リズムが舞台装置を超えて人に届くという性質上、商品のパッケージには『演者』も含まれる。そのため「表情」や「立ち姿」といった視覚的な領域から、SNSでの振る舞い、思想、発言などが全て商品の一部となる。アイコン的な存在を商品の中に組み込めれば、認知度は拡散されやすく、固定ファンも付きやすくなる。
③ 【世界観=ブランド】と【売れるパッケージ=商品】」の統合
最後に【世界観=ブランド】と【売れるパッケージ=商品】」の統合をし、『価値の届け方』を定めていく。自身の価値を届けるために『どのようなサービスを提供するのか?』をこれまでまとめてきた情報をもとに形にし、それを世界観=ブランドに当てはめていく。商品パッケージは「価値の届け方」を定めることで自ずと輪郭が見えてくる。あとはそれを自身の言葉で定義し、形に落とし込んでいくだけである。
『自身が提供できる価値』『価値が顧客に与える変化』『価値を構築する世界観』を重ねる作業は一回で完成することはない。何度も調整が必要になるフェーズだ。
しかし、どれだけ複雑に見えても「価値を提供する代わりに、報酬をいただく」という基本構造は変わらず、顧客は「自身の抱える問題を解決した・満たされた」時に対価を払う。
ステップ4:届ける手段(チャネル)を選び、市場に参入する
価値の届け方=商品化の設計がある程度まとまったら、次は『商品を顧客に届ける手段=チャネル』の選定へと移る。
ここのフェーズに関しては『あくまで初期フェーズにおいて、限られた予算を当てる場所を選ぶ』ことに関して解説するものとする。なぜなら、チャネル戦略含むマーケティング活動は常に考え、実行する必要がある領域であり、未来の方針まで簡単に決めることができなからだ。
チャネルとは、集客するための媒体、経路のことを意味するマーケティング用語である。商品を見込み客へ周知させ、関係性を生み出せなければ営業することはできない。
『良い演奏ができれば、依頼が来る』ことは難しく、特に高額報酬の案件を獲得したいのであれば積極的なコミュニケーションは不可欠である。そこで重要になるのが『接点となる場』だ。
市場に対して『どのような形で接点を持つか』という問いに対して、自身の手元にある環境や武器を用いて、どのチャネルが自身にとってスムーズに参入できるのかがイメージできるのであれば、次は行動に移すのみである。
| チャネル | 特性・性質 |
|---|---|
| Instagram, TikTok等のSNS | 写真や動画で感性・視覚訴求が可能 |
| YouTube | 長尺の動画コンテンツを発信できる |
| 自団体・個人のサイト | 商品の詳細を発信でき、かつ窓口となる |
| 交流会 | 名刺交換によって直接関係を持てる |
| 教育機関との提携 | 芸術鑑賞会、文化講座、教材提供 |
| 文化庁/地方自治体 | 地域芸能振興、移住・地方活性化との連携 |
最初に『自団体・個人のサイト』を簡易的でもいいので作ることを筆者は推奨している。なぜなら、サービスを紹介する媒体がなければ、具体的に見込み客に向けて営業を仕掛けることができないからだ。また、何よりも重要なのは『問い合わせ先』をしっかりと作り、訴求することである。せっかく受け皿となるWebサイトを作っても問い合わせフォームがなければ案件を獲得することは難しい。
市場を定め、パッケージを決め、届け方・手段を決めたら、後は情報を発信し、接点を持ち、営業を常にし続けることだ。ここからの行程は非常に泥臭いが、一歩ずつ積み重ねていく先に経済的成功が微笑む。
この『マーケティング』に関する領域は非常に深く、これだけで何記事も執筆できるため、本稿では紹介までとする。具体的な解説は別記事を投稿していく予定なので本サイトをチェックしてもらえると幸いある。
まとめ:ボランティアから抜けるために『価値』を明確にせよ
本稿は和太鼓奏者が抱えるボランティア性から脱却するための方向性として『資本主義への適応』という道を示し、そこに向かって歩くための準備するべき事柄を解説したものである。
和太鼓は世界的に見ても非常に稀な『文化資本としての価値+公共財としての性質』を持つ楽器である。
そのため、経済的成長を得るためには『価値を言語化』し『自身の価値が刺さる市場を選ぶ』ことが何よりも大切になる。そして、自身が提供できる価値を『商品としてパッケージ化』して、それを売り込む『チャネル及び接点を持つための施策』を選定し、毎日コツコツと積み上げていく。
マーケティング活動は地道で泥臭いものだが、しっかりと積み上げていけば強力な力となる。また、経済的成功を手に入れるためには並行して奏者は技術を磨き続け、舞台表現を唯一無二のものへ昇華させることも欠かせない。
太鼓日和では今後も和太鼓市場を活性化させるために経済的・文化的・社会的・芸術的視点の記事を執筆していく。マーケティングに関する相談や依頼がもしあれば気軽に問い合わせしてほしい。
参考文献
書籍
・事例で学ぶ BtoBマーケティングの戦略と実践
・ブランディングの科学 誰も知らないマーケティングの法則11
・コトラー&ケラー&チェルネフ マーケティング・マネジメント〔原書16版〕