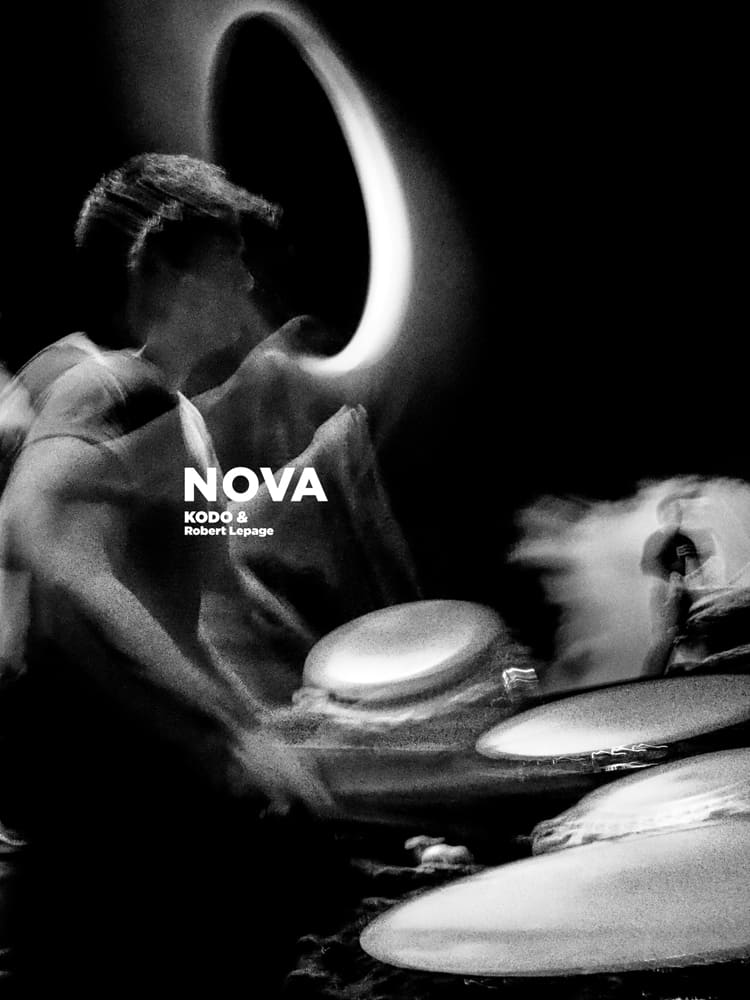近代(江戸、明治、大正)
江戸時代:日本芸能の全盛と太鼓文化の隆盛
江戸時代(1603年〜1868年)は、平和な社会秩序の中で町人文化が花開き、日本文化の多様な形式が大成した時代です。芸能や音楽、美術など、さまざまな分野で独自の発展が見られたが、和楽器を用いた音楽文化もこの時期に大きな進化を遂げます。その中でも、太鼓は音楽的・文化的双方において重要な地位を占め、現代の太鼓文化の礎を築いた重要な時代と言えます。
太鼓は神社仏閣の祭礼や村落の年中行事、都市部の娯楽空間など、宗教・民俗・芸能の多様な場面で広く用いられるようになり、日常生活と深く結びついた楽器としてその地位を確立していきました。たとえば、京都の祇園祭や江戸の神田祭の山車行列では、太鼓が練り歩く囃子の中心となり、人々の高揚感を生み出し、祭のボルテージを最高潮まで高める装置として機能しました。
農村においては、田植えや収穫の儀礼において五穀豊穣を祈願する宗教的・共同体的な実践に太鼓は組み込まれていき、儀式的な側面を持ちつつもエンターテイメントとしての側面も持ち合わせるようになっていきます。
また、都市の娯楽施設である芝居小屋や寄席においても、太鼓は不可欠な存在でした。歌舞伎では、場面転換を演出する「ツケ打ち」や、囃子方による下座音楽に用いられ、登場人物の感情表現や舞台の緊張感を高める要素として使用されます。
江戸期は落語や講談といった話芸が盛んであり、話芸のみならず多くの曲芸を楽しめた寄席では、出演者の登場を告げる「出囃子」や、開幕の合図である「呼び太鼓」など、聴衆の注意を引き、演芸の始まりを知らせる役割を果たしました。
当初、太鼓は笛や三味線など旋律楽器を支えるリズム楽器としての役割が主であったが、やがて太鼓そのものを主役とする演奏文化も芽生え始めます。その象徴的な例が、「のら打ち」と呼ばれる自由打ちの集まりです。「のら打ち」は、特定の楽譜や形式にとらわれず、個々の奏者が技術や創意を発揮する即興的な演奏の場であり、主に町人や農民、職人階層の若者たちによって夜間に寺社の境内、門前町の広場、あるいは河川敷などで催されたとされています。
このような集まりでは、音の迫力や打ち手の技量を競い合うことが娯楽となり、地域によっては「太鼓名人」として知られる人物が登場するなど、演奏の芸術性が重視される傾向が強まっていきました。とくに江戸や大坂といった都市圏では、職人町の青年層を中心に、非公式ながら太鼓の演奏会や技芸競演のような形で「のら打ち」が繰り広げられていたと伝えられています。このような現象は、太鼓が単なる伴奏楽器にとどまらず、自律した演奏主体として芸術的・娯楽的価値を獲得しはじめたことを意味します。
江戸時代を通じて、太鼓は宗教儀礼、芸能、民俗行事、都市の娯楽文化に浸透し、社会階層や地域を越えて多くの人々に親しまれる存在となっていきました。
太鼓製造業の勃興と職人文化
江戸時代には、現代にも継承される太鼓製造の老舗が次々と創業しました。1609年には浅野太鼓楽器店の前身となる皮革業が創業され、後に日本最古の太鼓メーカーとして知られるようになります。同社は、江戸初期から現代に至るまで、和太鼓文化の発展に大きく寄与してきた最重要企業の一つです。
以降も、1717年に杉浦太鼓店、1789年に三浦太幸堂、1833年に中島太鼓店、1835年に岡田屋布施、1861年に宮本卯之助商店といった名だたる老舗が次々に創業され、太鼓製造業が隆盛を迎えます。これらの企業は、神社仏閣や能楽・歌舞伎座に楽器を納めるなど、芸能と宗教の両領域において重要な役割を果たしました。
また、三崎屋太鼓店やアサノ楽器(三味線・琴を主に製造)など、地域の芸能保存団体や民俗芸能と密接に関わるメーカーも同時期に誕生しています。これらの工房は、伝統技術の継承と革新を担いながら、和太鼓の製造と普及に貢献してきました。1870年(明治3年)創業の丸岡太鼓店は、江戸末期に太鼓職人として修行を積んだ丸山庄五郎によって創業されたものであり、江戸期の技術を近代に継承する重要な事例の一つです。
こうした職人文化の中で作られた太鼓の中には、現在でも使用可能な状態で残っているものもあり、江戸時代の「音」が現代にまで伝えられています。
部落産業と和太鼓製造の関係
太鼓の製造には、日本社会の歴史的構造の中で被差別とされてきた人々(いわゆる被差別部落の出身者)が深く関与しています。とりわけ、皮革加工や木材加工など、「穢れ」に関係するとされてきた生業に従事することを制度的・社会的に強いられてきた彼らは、その中で極めて高度な専門技術を発展させました。
太鼓製造においては、牛や馬の皮を用いた鼓面づくりや、クスノキやケヤキなどの硬質木材をくり抜く胴体加工といった工程が必要不可欠であり、これらはまさに部落民が伝統的に担ってきた職能と合致していました。その結果、江戸時代には身分制度の下、士農工商の枠外に置かれた「穢多・非人」といった人々が、社会的に忌避される一方で、仏教や神道における儀礼に不可欠な楽器の供給を担うという、矛盾した存在として位置づけられていました。
彼らが作る太鼓は、神社仏閣の祭礼や芸能、さらには武士の儀式など、あらゆる領域において欠かすことのできない文化的基盤を形成することになります。多くの伝統工房では、完成した太鼓の胴の内側に職人が自らの名を彫り込む習慣があり、これは職人としての誇りと、世代を超えて継承される技術への自負を示すものでした。
このように、太鼓が表舞台で華やかに響き渡る一方で、その背後には被差別民による精緻な技術と労働の積み重ね、そして社会的分業と階層構造が存在していました。太鼓の音には、表層からは見えにくい社会史の響きもまた、確かに刻まれているのです。
私たちが目にする太鼓に関する文化は彼らが生きた証であり、私たち現代の太鼓打ち並びに日本文化を享受する全ての人たちはこの事実をしっかりと学ぶ必要があります。彼らの誇りをしっかりと受け取り、感謝の念を抱き、尊重し、彼らの魂の安寧を祈る…それが現代に生きる私たちができる職人たちへの餞であると筆者は信じています。
芸能との共振:歌舞伎における下座音楽での発展
江戸時代に成立・発展した歌舞伎は、太鼓の演奏技術と表現力を飛躍的に進化させた舞台芸能です。とりわけ、舞台下手(しもて)の床下に控える演奏者たちが担う下座音楽において、太鼓は三味線、笛、小鼓、大鼓などとともに主要な楽器として位置づけられました。下座音楽とは、歌舞伎の場面展開を音楽で支え、登場人物の感情や場の雰囲気を聴覚的に演出するための伴奏音楽です。
この下座音楽において、太鼓は単なる拍子取りを超え、「ドン」「カッ」「ドドン」などの多彩な打音によって、雷鳴、戦の緊張、心情の動揺、あるいは幽霊の登場といった劇的効果を具現化する音響装置として活用されました。たとえば『仮名手本忠臣蔵』の討ち入り場面では、大太鼓の重厚な連打が登場人物の決意や緊張感を高め、観客の没入を促す要素となっています。
また、場面の性格に応じて太鼓の種類と演奏法が細かく使い分けられた点も特筆に値します。たとえば、戦闘や動的な場面では大太鼓が用いられ、静謐や不安を強調したい場面では締太鼓が採用されるなど、技法と構成が体系化されていきます。こうした実践の蓄積は、太鼓が「語る楽器」すなわち情景や心理を描写する音楽的主体としての地位を確立する契機となりました。
このように、歌舞伎という総合芸術の中で太鼓は、視覚的な演技と連動する聴覚的な演出手段として進化し、その後の邦楽(例:長唄、常磐津など)、民俗芸能(例:神楽、獅子舞、祭囃子など)、さらには現代の創作太鼓(例:鼓童、鬼太鼓座など)に至るまで、多方面の芸能文化において演奏法や音楽観の発展に寄与し続けています。
日本舞踊と太鼓
江戸時代は、日本舞踊が急速に体系化・洗練され、都市文化の中で大きな発展を遂げた時代でもあります。巫女舞や稚児舞など神事芸能に起源をもつ舞に加え、地歌舞や上方舞のような町人層に支えられた舞踊様式が成立し、やがて藤間流(初代藤間勘兵衛、1704年創流)、若柳流(初代若柳吉蔵、1815年創流)、花柳流(初代花柳壽輔、1849年創流)など、今日に至る日本舞踊の主要流派が誕生・確立していきます。
これらの舞踊は、視覚的な身体表現にとどまらず、音楽と密接に連動する総合芸術として発展したが、その音楽的基盤として不可欠だったのが、太鼓を含む囃子方の存在です。
囃子方とは、舞踊において音楽演奏を担う専門の演奏家集団であり、長唄、清元、常磐津などの音楽ジャンルにおいて、太鼓、締太鼓、鼓、大鼓、小鼓、笛などを用いて舞台演出を支えました。
囃子文化と大衆娯楽
祭囃子は、日本各地の祭礼において中世以前から演奏されてきましたが、特に江戸時代において、都市化の進展および地域共同体の再編・強化とともに洗練され、地域固有の芸能として各地に定着しました。
囃子の構成は、太鼓・笛・鉦・鼓などの和楽器による合奏を基本とし、神輿の渡御や山車の巡行、獅子舞などの儀礼的・祝祭的行事において、聴覚的な高揚感と視覚的な賑わいをもたらす要素として重要な役割を果たします。
とりわけ、曳山(山車)文化との結びつきは顕著であり、「京都祇園祭」「岐阜高山祭」「秩父夜祭」は「日本三大曳山祭」として広く知られています。
これらの祭礼においては、精緻に装飾された山車と、その上で演奏される囃子が一体となり、地域住民による芸能伝承や地域アイデンティティの形成に寄与してきました。加えて、「花輪ばやし」(秋田県鹿角市)、「飾山囃子」(福岡県博多)、「富士宮囃子」(静岡県富士宮市)など、地域の大祭に根ざした囃子芸能も独自の発展を遂げています。
江戸の都市文化においては、「江戸祭囃子」が高度に様式化され、とりわけ葛飾地域を中心に成立した「葛西囃子」は江戸型祭囃子の代表格とされます。軽快なテンポ、掛け声との連動、緻密なリズム構成を特徴とし、現在に至るまで地域行事や郷土芸能として継承されています。同様に、神田祭における「神田囃子」、品川の「品川拍子」、目黒の「目黒囃子」、羽田の「羽田囃子」、深川の三社祭における「三社祭礼囃子」など、江戸市中の町々でも多様な囃子が発展し、町人文化の一翼を担う芸能として現代でも親しまれています。
江戸近郊および関東各地でも、地域に根ざした囃子文化が形成されました。たとえば「佐原囃子」(千葉県佐原)は、豪華絢爛な山車との共演によって関東を代表する祭囃子として発展し、「重松囃子」(東京都東久留米市周辺)は多摩地域一帯に伝承されています。また、「新川囃子」「西三ツ木ばやし」「日高囃子」なども、それぞれの地域社会の年中行事に密着しながら、世代を超えて受け継がれています。
関東以外の地域においても、神奈川県の「鎌倉囃子」「小田原囃子」「真鶴囃子」「排禍ばやし」「岩囃子」「浜の手流」などは、江戸との地理的・文化的な近接性を背景に独自の様式を発展させました。関西以西では「祇園囃子」や、伊勢信仰と結びついた「伊勢音頭」、大阪・堺を中心とする地車(だんじり)祭に由来する「地車囃子」などが顕著です。とりわけ地車囃子は、勇壮な曳行と一体化し、町人の活力と地域の結束を象徴する芸能として機能しました。
九州においても、独自の祭囃子文化が形成された。たとえば熊本県の「ボシタ囃子」、宮崎県の「鴻八幡宮祭りばやし」などは、地域信仰や風土と深く結びついた形で、現代に至るまで伝承されています。
このように、江戸時代を通じて発展した祭囃子は、都市部・農村部を問わず、各地域の歴史・信仰・社会構造と密接に結びつきながら、視覚・聴覚・身体的参与を伴う「総合芸能」として日本の祭礼文化に深く根付きました。そして、その中核にある太鼓は、単なる打楽器を超えて、「音による共同体形成装置」としての役割を果たしています。
明治時代:近代化と西洋音楽導入による文化構造の転換
明治時代における西洋音楽導入政策は、日本の芸能文化に対して極めて大きな影響を及ぼしました。明治12年(1879年)、文部省に「音楽取調掛」が設置され、伊沢修二を中心に西洋音楽教育の制度化が進められました。当初はアメリカ式の音楽教育が参照されていましたが、後により理論的体系が整っているドイツ式音楽理論へと移行し、教育用唱歌の普及が図られます。
『小学唱歌集』のような教材が全国の小学校で使用されることで、音楽教育は「唱歌=音楽」という等式を生み出し、音楽の標準が「旋律中心・和声的・譜面に基づく」形式へと固定されていきました。この動きの中で、即興性や身体性を重視する和楽器を用いた音楽は「非科学的」「前近代的」と見なされ、教育現場から排除されるようになります。
一方で、地方の祭礼や地域行事においては、こうした政府の方針とは異なる文化実践が継続されていました。祭囃子や神楽といった伝統芸能においては、太鼓は依然として重要な役割を果たしており、地域共同体の結束や信仰実践と深く結びついていました。しかし、こうした民俗芸能は明治政府の中央集権的な文化政策のもとでは「近代化から取り残されたもの」「文化の遅れを象徴するもの」として扱われ、意図的に「民俗=非近代」の枠組みに押し込められていきます。
このように、明治期の音楽政策および文化政策は、太鼓を含む芸能文化を「芸能」の枠組みから排除し、「民俗」の領域へと追いやる働きをしました。この構造的転換は、単なる趣味や好みの問題ではなく、教育制度・都市政策・風紀規制・思想統制といった国家的装置を通して制度的に遂行されたものです。その影響は戦後の芸能再評価以前まで長く続きましたが、1950年代以降の日本太鼓復興運動において、こうした周縁化された文化が再び注目され、新たな文化的価値として再構築される土壌が形成されていきます。
伝統芸能としての和太鼓の維持と地域的多様性
明治維新以降、日本は「富国強兵」「殖産興業」「文明開化」といったスローガンのもと、急速な近代国家の構築を推進しました。この過程で、伝統的な宗教儀礼や地域芸能、民間信仰は「迷信」「非文明的」として排除・変容の対象となっていきます。
特に都市部においては、警察条例や衛生政策、都市計画の進行、さらには音環境の整備などにより、盆踊りや祭礼囃子などの民衆芸能は「騒音的」「非近代的」と見なされ、公共空間から徐々に姿を消していきます。このような規制は明治期から大正期にかけて法的にも強化され、伝統芸能は近代都市の「秩序」と衝突することが多い時代でした(例:1880年代の東京の祭礼禁止令など)。しかしながら、これらの政策に対しても地域住民は必ずしも一方的に抵抗するだけではなく、変化を受容しつつ、新たな祭礼の形式や公共行事の創出など柔軟な適応も見られました。

一方、地方農村部においては生活の近代化が比較的緩やかであったため、江戸期以来の祭礼、年中行事、信仰儀礼といった民俗的実践は、地域共同体の生活リズムの中で継続的に保持されました。例えば東北の「ねぶた祭」や九州の「博多祇園山笠」など、各地の祭礼は地域の歴史的・宗教的背景に基づいて独自の進化を遂げつつ存続しました。こうした地域社会において、和太鼓を中核とする伝統芸能は、単なる娯楽の域を超えて、宗教・労働・教育・娯楽の諸側面を統合する象徴的・機能的装置として存在しました。
太鼓が活用された主な芸能形態は以下のとおりです。
- 神楽:
神社の祭礼儀礼において、太鼓は神霊の降臨を促す神聖な鳴り物として位置づけられた。 - 祭囃子・盆踊り:
地域の年中行事において拍子の核をなすとともに、各地に固有の打法、旋律構造が世代を超えて継承された。 - 寄席囃子:
都市の話芸において、場面転換や感情表現を支える演出音楽として機能した。 - 四拍子:
能楽における伝統的な拍子音楽において、笛・小鼓・大鼓とともに太鼓が重要な役割を果たした。 - 下座音楽:
歌舞伎舞台において、人物の動作・心情・時間の流れを音響的に可視化するための伴奏として用いられた。 - 民謡伴奏:
農耕儀礼や生活の中に根ざした民謡において、太鼓はリズムの担い手として地域固有の拍節感を表現した。
明治国家が進めた中央集権的な文化政策のもと、多くの民間芸能は衰退や標準化を余儀なくされる一方で、太鼓は地域社会に根ざしたローカルな演奏文脈を保持しつつ、近代的な文化再編成の圧力に対して独自の持続性を発揮していきます。加えて、国家主導による「伝統芸能」の選別・保護政策では、能楽や歌舞伎が「国民文化」として制度的に位置づけられたのに対し、多くの地域芸能は「民俗芸能」として学術的・保存的対象となり、その保存や継承は地方自治体や民間団体に委ねられる傾向が強くありました。
この過程は地域文化の多様性の維持と同時に、その周縁化や制度的保護の限定性という課題も孕んでいます。地域芸能はしばしば「民俗芸能」として周縁化されました。しかし、そのような周縁的実践の中にこそ、日本列島における芸能文化の多層性と多様性が内在し、太鼓はその多様性を具現化する重要な身体的・聴覚的メディアであり続けたのだと言えます。
都市型芸能の変容と和太鼓の再評価
都市部においても、太鼓は存在そのものが完全に排除されたわけではありません。明治22年(1889年)に東京・銀座に新たな歌舞伎座が創設され、これは歌舞伎の近代化および大衆化を象徴する重要な出来事でした。九代目市川團十郎や五代目尾上菊五郎らの指導のもと、伝統的な様式に加えて写実的演技技法(例えば、人物の心理表現の細密化や動作の自然主義的演出)が導入され、舞台装置や照明の近代化が進んでいきます。
これにより、従来「低俗芸能」として否定的に見られていた歌舞伎は、西洋的なリアリズム演劇や美学の影響を受けつつ、日本伝統の演劇様式との融合を試みる形で再評価されていきました。このような近代化の動きの中でも、太鼓は歌舞伎の下座音楽として重要な役割を保持し続けます。
大正期における都市芸能の展開と和太鼓の再定位
大正時代(1912〜1926年)は、大衆文化の台頭と芸術の近代化が並行して進行した時代で、多くの芸術運動が国内で起こり、日本独自の思想観が形成されていく文化的に非常に重要な時期です。
その中で太鼓は、新聞や雑誌、レコードといったメディア芸能・新劇・無声映画といった新たな領域に進出するとともに、地域社会の記憶やアイデンティティを支える存在としても再構築されていきました。太鼓はこの時代において、芸術的・文化的再定義を遂げた多義的なメディアとして位置づけられ、日本文化の核を支える土台として多くの表現に姿を表す『現代和太鼓』の基礎として強い存在感を放っていました。
都市芸能とメディアの拡張――大正ロマンと大衆文化の形成
第一次世界大戦後の国際秩序の変動や自由主義・民主主義思想の高まりを背景に、「大正デモクラシー」と称される自由主義的文化が都市部を中心に広がった時代です。この時代には、個人の感性や内面の自由を重視する芸術至上主義や感情表現を尊ぶ潮流が強まり、これらは欧米のロマン主義の影響を受けつつも、日本独自の都市文化として結実し、のちに「大正ロマン」と総称される文化現象を形成しました。
都市空間においては、新聞、雑誌、レコード、映画といったメディア技術の発展と普及によって、芸能や音楽に触れる機会が飛躍的に拡大していきました。
1912年に創立された吉本興業は、寄席や漫才といった大衆芸能を組織的に運営・普及させる体制を整えました。また、同年に設立された日活は、日本映画の初期黄金期を牽引し、のちの時代において芸能が「商品」として全国的に流通する基盤を築いたといえます。こうした動きによって、それまで地域に根差していた芸能や音楽が、都市文化と結びつきながら新たな意味や価値を獲得していくようになりました。
映画の分野では、無声映画において活動弁士とともに演奏された伴奏音楽のなかに和楽器が用いられることもありました。これにより、太鼓は従来の「神事・民俗芸能」的な機能から、都市型娯楽における演出的な要素としての位置づけへと変化し始めたと考えられます。
日本文化の再評価と和太鼓の地域芸能への回帰
一方で、大正期に加速した西洋化および工業化の進展は、日本の伝統文化や生活様式に急激な変容をもたらすと同時に、それに対する批判的な省察や「固有文化」への再評価の機運を生み出しました。このような潮流の背景には、柳田國男による常民(一般庶民)に着目した民衆文化研究の展開や、折口信夫による芸能起源論の構築といった、後の民俗学につながる知的動きがありました。これらは雑誌媒体や実地調査を通じて共有され、学問的枠組みへと発展し始めていたといえます。
とりわけ、柳田國男の『郷土研究』や『後狩詞記』に見られる農村文化への関心は、近代化の波のなかで見過ごされがちな地域文化に対する注視を促す契機となりました。
また、折口信夫は芸能を宗教儀礼に由来する祝祭的表現と位置づけることで、庶民の芸能に宗教的・文化的な深層を読み取り、芸能の文化資源としての価値を再評価する理論的基盤を提示しました。
こうした文化的反動の中で、民俗芸能や郷土文化の再発見・再定義を目的とする諸運動が、1920年代以降に全国的に展開されるようになりました。その中心的な媒体の一つが、1925年に創刊された雑誌『民俗芸術』です。これは折口信夫が主宰し、柳田國男や鳥居龍蔵といった民俗学・人類学・芸能史の研究者が関与した学際的な論壇誌であり、盆踊り、念仏踊り、神楽、田楽、囃子など、農村部に根ざした芸能の記録・分析・再評価を目的としていました。
誌面では、これらの芸能がもつ芸術的構造、地域ごとの変異、宗教儀礼や社会組織との関係といった観点から多角的に論じられ、従来「素朴」あるいは「前近代的」と見なされてきた表現に対する新たな文化的価値づけが試みられていきました。